1. ゲーム理論とは何か?
● 定義:
ゲーム理論とは、
「複数の意思決定者(プレイヤー)が、お互いの行動を考慮しながら最適な戦略を選ぶときの意思決定を分析する理論」
● ポイント:
- 相手の行動を読んで、自分の行動を決める
- 勝ち負けに限らず、「利得(利益・損失)」がどう分かれるかに注目
- 「戦略」「利得」「情報」「均衡」が中心
2. 経営におけるゲーム理論の意義
現実の企業経営では、競合他社や取引先、顧客の行動を予測して、自社の行動を決める必要があります。
たとえば…
- 新商品を出すか?
- 値下げをするか?
- 他社と提携するか?
こうした意思決定は、相手の出方によって成果が変わるため、ゲーム理論が役に立ちます。
3. 基本用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| プレイヤー | 意思決定を行う主体(企業、顧客、政府など) |
| 戦略 | それぞれが選ぶ行動(値下げ・提携・撤退など) |
| 利得(ペイオフ) | 戦略の組み合わせによって得られる利益や損失 |
| ナッシュ均衡 | 互いに最善の戦略を選び、どちらも戦略を変えない状態 |
| ゲームの種類 | 同時手・逐次手、協力型・非協力型、ゼロサム・非ゼロサムなど |
4. 代表的なゲームの例
● (1) 囚人のジレンマ(非協力ゲーム)
例:2社が値下げするかどうか
| 相手が値下げしない | 相手が値下げする | |
|---|---|---|
| 自社が値下げしない | 両者安定的に利益(5,5) | 自社が損(1,8) |
| 自社が値下げする | 自社が得(8,1) | 両者利益が下がる(2,2) |
→ 互いに「値下げする」がナッシュ均衡だが、結果的に損をする(ジレンマ)
● (2) チキンゲーム(撤退 vs 突っ込む)
→ 2社が同じ市場に進出し続けると赤字。どちらかが撤退すべき。
例:航空会社AとBが同じ地方路線を運航し続けるかどうか
- 両者が突っ込めば:共倒れ(赤字)
- 一方が引けば:残ったほうが市場を独占(利益)
→ 互いに相手の出方を見ながら度胸比べになる
● (3) 価格リーダーシップ(逐次ゲーム)
→ 先に行動した企業が「価格リーダー」として市場を支配
- 先手企業が価格を決め、後手が追随
- 先手が優位になりやすい(first-mover advantage)
5. ナッシュ均衡とは?
● 定義
すべてのプレイヤーが最善の行動を選び、他の誰かが戦略を変えても自分の利得が改善されない状態
→ 「誰も得しないので、今の状態から動けない」
● 経営への応用
- 値下げ合戦で互いに抜け出せない状況
- 買収・合併の駆け引き
- 価格維持の暗黙の了解(カルテルに近いが合法の範囲)
6. ゲーム理論を使った経営戦略の具体例
(1)価格戦略
→ 競合の値下げにどう対応するか?
→ 無理に対抗せず「差別化」で勝負する戦略もある(ナッシュ均衡を崩す)
(2)参入障壁の構築
→ ゲーム理論では、「脅し(threat)」も戦略の一部
→ 例:大企業が「価格戦争に持ち込むぞ」と示すことで新規参入を防ぐ
(3)提携や合併
→ 競争状態から協調関係に変化させて、ゲームの構造そのものを変える(ゲームの再設計)
(4)時間的優位の活用
→ 最初に行動して主導権を握る(first mover)か、後出しで学習して勝つ(second mover)
7. 限界と注意点
- 実際の企業行動は完全情報ではない(情報の非対称性がある)
- 感情や直感、文化、倫理観など非合理要素も現実には強い
- ゲーム理論はあくまで戦略的思考の補助ツール
8. まとめ
「相手の出方によって自分の成果が変わる」ような状況では、
ゲーム理論的な思考=相手の立場に立って考えることが非常に重要です。
企業の経営判断、交渉、競争戦略、協業判断において、
「相手も考えている」ことを前提にした意思決定こそがゲーム理論の本質です。
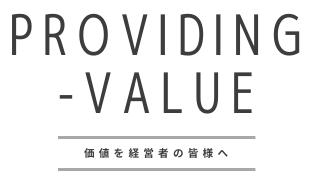
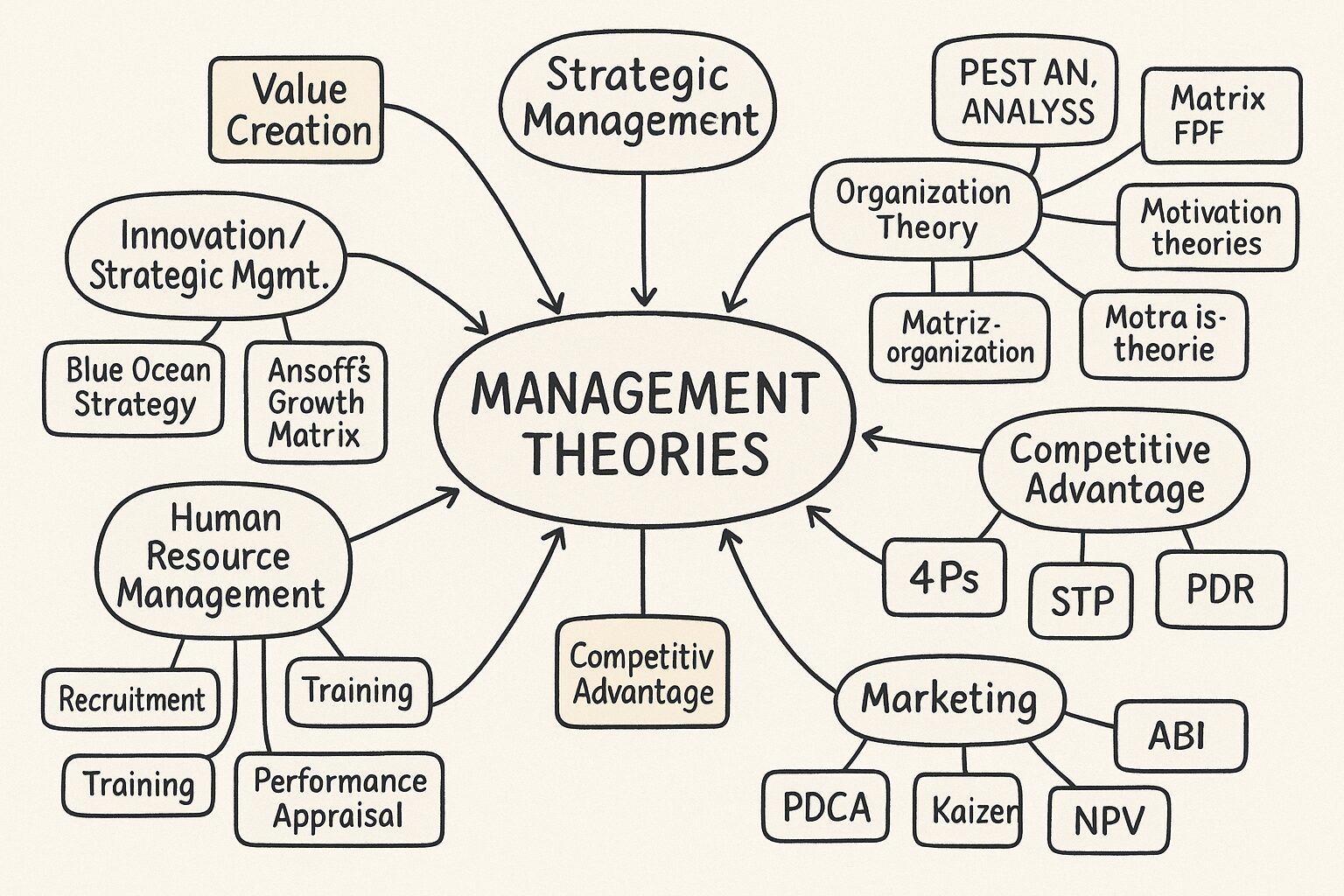


コメント