🔷 SCP理論の基本フレームワーク
plaintextコピーする編集するStructure(市場構造)
↓
Conduct(企業行動)
↓
Performance(業績・成果)
この「上から下」への因果関係が基本ですが、実際の市場では「成果が構造に影響を与える」ようなフィードバックループもあります。
各要素の具体的内容と観点
① Structure(市場構造)
これは「市場環境の骨格」であり、企業が行動する舞台を形づくるものです。
分析観点:
- 市場集中度:上位企業のシェア(CR4, HHIなど)
- 参入障壁:特許・ブランド・初期投資の大きさ・法規制など
- 製品の差別化度:標準化商品か個性があるか
- 需要の価格弾力性:価格変動に対する消費者の反応度
- 規模の経済:生産量が増えるとコストが下がるか
- 技術構造や流通構造:サプライチェーンの支配関係など
② Conduct(企業行動)
企業が市場の構造の中でどのようにふるまうか(戦略をとるか)という「意思決定の中身」です。
分析観点:
- 価格設定戦略:競争的価格?囲い込み型?
- 製品開発・研究開発(R&D):技術革新を重視するか
- 広告・販促活動:ブランディング重視か
- 設備投資・流通支配:インフラの自社化、系列化
- 企業間関係:競争か協調か(カルテル、ジョイントベンチャーなど)
③ Performance(成果)
企業・産業のふるまいの結果として得られるパフォーマンス(経済的・社会的成果)です。
分析観点:
- 利益率・成長率:財務指標
- 技術革新の成果:新製品、新技術の登場頻度
- 資源配分の効率性:無駄がない生産構造か
- 消費者福利:価格の妥当性、選択肢の多さ
- 公平性:市場内の中小企業と大企業の格差、地域間格差など
🔁 フィードバックと循環的理解
近年は次のような双方向モデルで理解されることも多いです:
plaintextコピーする編集するStructure → Conduct → Performance
↑ ↓
└────────── Feedback ─────────┘
たとえば:
- 高収益(P)を上げた企業が、M&Aでさらに市場集中(S)を高める
- 技術革新(P)によって製品差別化が進み、企業行動(C)も多様化する
📌 フレームワークとしての使い方(実務例)
たとえば、ある業界に新規参入したい企業がいるとき、
ステップ1:Structure分析
「競合企業が寡占してるか?参入障壁は?顧客の選択肢は?」
ステップ2:Conduct分析
「競合他社はどんな価格・販促戦略をとっているか?非価格競争は?」
ステップ3:Performance分析
「その業界の平均利益率は?消費者満足度は?イノベーションは?」
これにより、「勝てる市場か」「どんな戦略で戦うべきか」「参入すべきでないのか」などの判断材料になります。
🔚 まとめ(SCP理論フレームワークの意義)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Structure(構造) | 市場の性質・制約を把握する |
| Conduct(行動) | 企業の戦略的ふるまいを分析 |
| Performance(成果) | 成果(収益・効率性・消費者利益など)を評価 |
| 因果関係 | 上から下への一方向が基本。ただし現実では双方向性あり |
このフレームワークを使えば、特定の産業が健全かどうか、競争環境が適切かどうか、政策介入が必要か、などを体系的に判断できます。
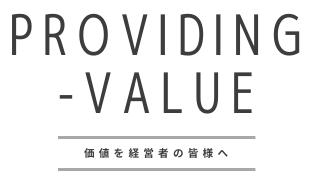
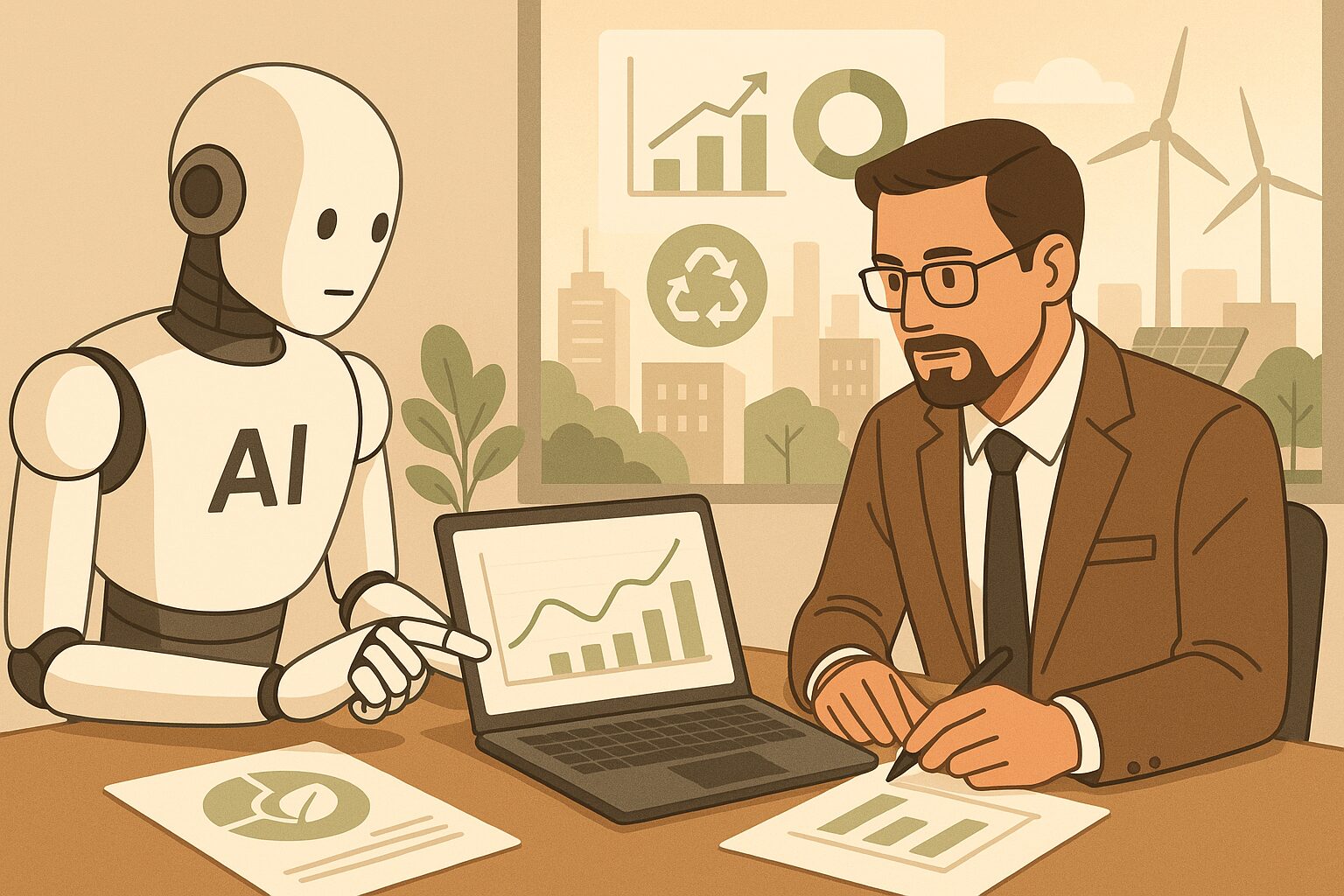

コメント